視覚的世界において、もし私が自らの像の存在に無自覚であったならば、世界はただ存在しているということになるでしょう。なぜなら、像という概念が存在しないのであれば、「私」が世界を見ているという意識も生じ得ないからです。そして、世界がただ存在しているのであれば、たとえば遠くの看板の文字がぼやけて見えた場合、それは実際にぼやけている文字としてしか把握されないでしょう。
しかし、ひと度これを内省すれば、私は現前する景色から自らの像を見出し、それが私秘的なものであり、その向こうには他者との共有物としての実物世界が存在する、ということを認識します。この時、世界は広大な存在であるのに対し、像は矮小化・実体視され、私の身体とほぼ同義のちっぽけなものとして理解されます。
さらに、両者の間には因果関係が成立することも見出されます。つまり、「物に反射した光が目に入り、それが電気信号として脳に伝わった結果、私に像が生じる」というものです。これは像が生じる原因が世界の側にあるということを示しています。つまり、視覚的世界から像を見出した途端に、私は自らの像が世界に対して受動的であることを知るのです。実際、私がどんなに抗おうとも、目の前にリンゴが置かれれば、私にはリンゴが立ち現れてしまうことは明らかでしょう。
同じように、現実世界において、もし私が自らの心的状態の存在に無自覚であったならば、世界はただ存在し、その時々の状況によって、ただ私の思いや言動が引き起こされることになるでしょう。なぜなら、心的状態という概念が存在しないのであれば、「私」が世界を認識し、思いや言動を為しているという意識も生じ得ないからです。そして、世界がただ存在しているのであれば、勉強がつまらないものとして立ち現れた場合、それはただつまらないものとしてしか把握されないでしょう。
しかし、ひと度これを内省すれば、私は自らの思いや言動と現前する景色から自らの心的状態を見出し、それが私秘的なものであり、その向こうには私の心的状態に色付けされていない客観的な現実世界が存在する、ということを認識します。この時、世界は強大な存在であるのに対し、心的状態は矮小化・実体視され、私の身体とほぼ同義のちっぽけなものとして理解されます。
さらに、両者の間には因果関係が成立することも見出されます。つまり、たとえば「勉強を前にして、脳のドーパミンが減少した結果、私のやる気が下がる」というものです。これは心的状態が生じる原因が世界の側にあるということを示しています。つまり、思いや言動を中心とした現実世界から心的状態を見出した途端に、私は自らの心的状態が世界に対して受動的であることを知るのです。
しかし、視覚的世界においては物の立ち現れが所与的であるのに対し、現実世界における私たちの思いや言動は自発的です。目の前にリンゴが置かれれば、誰にでもリンゴが立ち現れるのとは違い、ある状況に置かれたからといって、誰もが同じ思いや言動を為すわけではなく、正しい思いや言動が存在するわけでもありません。したがって、心的状態は受動的ではなく、私たちは日々自由に思いや言動を為しているはずです。
しかし、本当に自由に思いや言動を選択していると言えるでしょうか。もちろん、たとえば青信号で渡るかどうかといったことを毎回考えていれば、日常生活に支障を来たすことは明らかであり、必ずしも自由に思いや言動を為さなければならないわけではありません。しかし、それが人間性に関わるものであれば、話は別です。では、そのような場面において、私たちは自由に思いや言動を選択していると言えるでしょうか。
まず、視覚的世界において像を見出すのとは異なり、自らの思いや言動を中心とした現実世界から心的状態を見出すことは容易なことではありません。なぜなら私の中で去来する思い一つとっても、その中には内省による思考や迷い、判断といった様々なものが入り混じっていますが、その中から純粋な思いだけを取り出し、その心的状態を見出さなければならないからです。何より、本来、心的状態に明確な名称など存在しません。それは私たちが自らの心的状態を把握するために必要なものであって、言ってみれば、心的状態は如何様にも把握することができるのであり、その中でそれが偽りのないものであるかどうかを判断することは困難です。したがって、私たちは必ずしも自らの心的状態を正しく自覚できるわけではありません。
では、自らの心的状態に無自覚な場合、私にはどのようなことが起こるでしょうか。
たとえば、今私に勉強しなければならないという状況が生じているとします。そして、ここではまだ勉強に対して中立的な状態であるものとします。本来的に言えば、主体としての私というのは現実世界そのものなのですから、この状況そのものがすなわち無自覚な「私」だということになります。
しかし、実際の場面において、「私」に無自覚であることはほとんどありません。私たちは常にどこかで漠然と「私」というものを意識しています。この「私」は現実世界を内省することによって見出されるものであり、本来その状況そのものと同じものを意味するのでなければなりませんが、内省すると同時に矮小化・実体視されるため、その状況から独立した存在であり、なおかつ身体とほぼ同義のちっぽけなものとして把握されます。そうすると、勉強しなければならない状況というのは、「私」にとって対峙しなければならないものとして存在することになるでしょう。そして、仮に「私」に無自覚であれば、私は半ば所与的に思いや言動を為すはずですが、ここでは「私」を自覚しているのですから、私は自発的に思いや言動を為すことができます。
しかし、もしここで、私がその状況に反応する形で、たとえば「勉強がつまらない」という思いを抱いたり、実際に怠けたりしたとすればどうなるでしょうか。それは状況に対して受動的に思いや言動を為したということを意味するのです。つまり、私は「私」を自覚することによって自発的に思いや言動を為すことができますが、「私」を矮小化・実体視し、状況に反応する形で思いや言動を為すことによって、結果的に私は状況に対して自ら受動的な存在になるということです。
では、私が自発的であるにもかかわらず受動的であるならば、どのようなことが起こるでしょうか。
前章では、心的状態を受動的なものとして扱いました。つまり、自分の置かれた状況に反応する形で何らかの心的状態が生じ、それが私の思いや言動を引き起こすということです。これは像と同様、どのような状況でどのような思いや言動を為すかが予め決まっているということを意味します。リンゴが赤く見えるのをどうすることもできないように、勉強を前にして私につまらないという思いが芽生え、実際に怠けることは、私にはどうすることもできない事態だということです。しかし、もちろん実際には、視覚的世界が所与的であるのに対し、思いや言動には自由が与えられています。たとえつまらないという思いや実際に怠けようとする気持ちが引き起こされたとしても、それらを内省することによって思い留まり、また違う思いを抱くことができます。つまり、自発的に思いや言動を為すことができるわけです。
では、それによって何が起こるでしょうか。
それは、これまでとは逆に、今度はその自発的な思いや言動が心的状態に影響を与えるということです。仮に私が「私」に無自覚であったならば、思いや言動を引き起こす原因は心的状態だということになりますが、実際は現実世界を一時中断し、「私」を自覚することによって、心的状態を原因としない自由な思いや言動を為すことが可能です。そして、思いや言動と心的状態は同じ一つのものの二通りの解釈なのですから、今度はその思いや言動が原因となって心的状態に影響を与えることができるわけです。
ただし、もちろん一度や二度の思いや言動が心的状態に影響を与えるわけではないでしょう。しかし、私たちは日々、幾度となく自分の思いや言動を内省し、試行錯誤を繰り返しているのですから、それによって積み重ねられた思いや言動は確実に自分の心的状態に影響を与えているのです。そして、そのように日々の思いや言動が影響を与えているのであれば、心的状態は常に流動的で曖昧なものだと言えるでしょう。
では、その中で、私が自発的であるにもかかわらず受動的であるならば、どのようなことが起こるでしょうか。
たとえば、矮小化・実体視された「私」が勉強しなければならない状況に反応する形で「つまらない」という思いを抱いたり、実際に怠けたりすれば、その思いや言動が「やる気がない」状態を形成することになります。この時、私は「私」を自覚しているのですから、当然自らの意思で思いや言動を為していると考えます。つまり、自らの思いや言動の原因は自分だというわけです。しかし、実際には矮小化・実体視された「私」と勉強しなければならない状況という構図の中で、状況に反応する形で思いや言動を為しているわけですから、その原因は状況なのです。したがって、私は自らの意思で思いや言動を為しているつもりでいますが、その中で、状況が原因となって私の心的状態が形成されていることになるわけです。そして、そのような思いや言動が繰り返されれば、その心的状態は強固なものになっていくでしょう。
ちなみに、ここで言う心的状態は脳の状態とは別物です。なぜなら、脳の状態というのは目に見える物理的なものであり、単に現実世界に存在するものですが、心的状態は現実世界を内省して見出される私そのものであり、それ故、私に制御可能なものだからです。したがって、脳の状態はどんなに詳細に調べたとしても、結局は心的状態に還元されなければならず、私たちにとって根本的な問題であり、最終的に関心を寄せるのはいつも心的状態です。たとえば将来的に脳の状態を変化させることによって、「やる気がある」状態を形成することができたとしても、問題になるのはその心的状態が果たして私たちに有益であるのか、そもそもそのような行為をすること自体が望ましいものであるのかといったことなのです。
さて、では状況を原因として「やる気がない」状態を形成したならば、私に何が起こるでしょうか。
それは、再び勉強しなければならない状況に直面した時、勉強は私にとってつまらないものとして立ち現れるということです。なぜなら、そこには「やる気がない」状態が現実世界の内在的原因として働くことになるからです。無像論で明らかなように、目の前にリンゴが置かれれば、私にはリンゴの像が生じますが、前者のリンゴを内省すれば、そこには私の像が内在的原因として働いているのですから、後者のリンゴの像は目の前のリンゴの裡にすでに存在していることになります。同じように、私に何らかの心的状態が形成されていれば、私が何らかの状況に置かれた時、そこにはすでに私の心的状態が働いているのです。そして、そのようにしてつまらないものとして立ち現れた勉強を前にして、再び矮小化・実体視された「私」がその状況と対峙する構図で捉えられれば、再びこれに反応する形で「つまらない」という思いを抱いたり、実際に怠けたりすることになります。そうすると、その思いや言動が「やる気がない」状態をさらに強固にし、勉強をますますつまらないものにするのです。
したがって、私が現実世界に対して受動的に振る舞う限り、私は知らず知らずのうちに自らの思いや言動が反映された現実世界を立ち現し、そしてその自ら招いた現実世界に反応することによって再び同じ思いや言動を繰り返す、という循環の中で生きることになるのです。しかし、矮小化・実体視された「私」は現実世界と対峙しているのですから、現実世界は私とは無関係に立ち現れ、私は自らの意思で思いや言動を為していると把握されるでしょう。そして、それは私が心的状態に無自覚である限り、半永久的に続くことになります。
もちろん、このような「つまらない」という思いから「やる気がない」状態が見出されるといった例えは、あくまで単純化したものであり、思いや言動を中心とした実際の現実世界全体と心的状態との因果関係はこのように明確なものではありません。
したがって、通常私たちは自分の思いや言動がどのような心的状態を形成し、それがどのように現実世界に反映されているかはわからず、それどころか自分の心的状態を把握しようとさえしないと言えるでしょう。そうすると当然、現実世界の原因は現実世界の側に存在することになります。勉強がつまらないのであれば、その原因はつまらない勉強のほうにあるのであって、自分の心的状態に求める必要はないのです。さらに、私は勉強を前にしただけで「つまらない」という思いを抱くわけですが、私が「やる気がない」状態に無自覚であれば、それが受動的な反応だとは気づかず、ただ自発的な思いだというだけの理由で、私はそれを自らの意思だと捉えます。
そうすると、私は矮小化・実体視された「私」を自覚しつつ、ただ強大な現実世界の前に立ちすくむしかないちっぽけな存在として、楽しいことがあれば楽しいと思い、つらいことがあればつらいと思うという受動性の中で生きていくことにも、幾らか主体性を見出すでしょう。しかし、それは本当に自由に思いや言動を選択しているとは言えないのではないでしょうか。
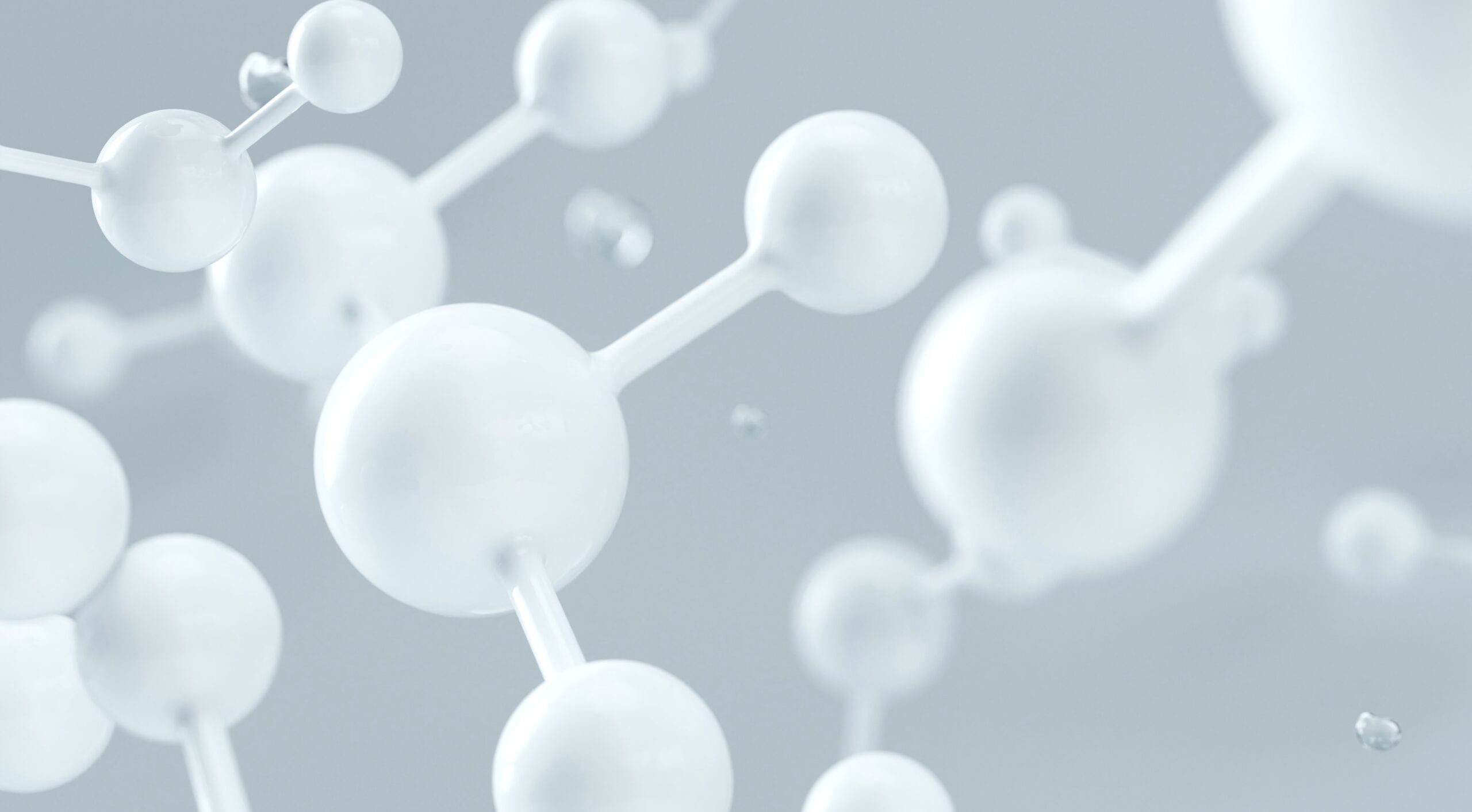

コメント